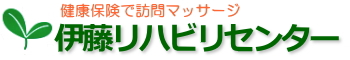東洋医学の視点でみる”介護予防”のコツ 袖ケ浦市、木更津市の訪問鍼灸マッサージ 伊藤リハビリセンター
いつもブログをご覧になって頂き本当にありがとうございます。
袖ケ浦市、木更津市の訪問鍼灸マッサージ 伊藤リハビリセンター(イトー鍼灸院)です。
当院では難病や病気の後遺症により自力通院が難しい方を対象に在宅にてリハビリマッサージや鍼灸施術を行なっています。
ご利用者様の生活環境は様々で、施設に入所されている方、お一人暮らしの方、ご家族と同居の方などなど…
私自身もですが、年齢を重ねるにつれて心配になるのが「介護が必要になるかもしれない」という不安。
でも、東洋医学の考え方を日常生活に取り入れることで、心身のバランスを整え、介護が必要になるリスクを減らすことができます。
この記事では、東洋医学的な「介護予防のコツ」をご紹介します。
- 「未病を防ぐ」=病気になる前にケアを
東洋医学では、「未病(みびょう)」という考え方があります。
これは「まだ病気ではないけれど、健康とも言えない状態」を指し、この段階で体調を整えることがとても重要だとされています。
✅コツ:体調の小さな変化を見逃さない
・食欲の変化
・睡眠の質
・便通の乱れ
・舌の色や形の変化
こうしたサインを日々チェックすることで、早めのケアが可能になります。
- 「気・血・水」の巡りを良くする
東洋医学では、健康とは「気・血・水(き・けつ・すい)」が全身をスムーズに巡っている状態と考えられています。
巡りが悪くなると、冷え・むくみ・疲れ・痛みなどが出やすくなり、身体機能が低下します。
✅コツ:簡単な運動やツボ押しを習慣に
・毎日の散歩
・足の裏をもむ
・「湧泉(ゆうせん)」「太渓(たいけい)」など、足のツボを押す
これだけでも、気血水の巡りをサポートできます。
- 「五臓六腑」をいたわる生活を
東洋医学では「五臓」(肝・心・脾・肺・腎)がそれぞれ心身の働きをコントロールしているとされています。
特に高齢期には、「腎」の衰えが老化と関係すると言われています。
✅コツ:腎を補う食養生
・黒豆、黒ごま、山芋、くるみなどを食事に取り入れる
・塩分や冷たい物を控えて腎を冷やさない
こうした「腎を守る食べ方」を意識することが、体の底力を高めることにつながります。
- 季節ごとの養生で自然と調和する
東洋医学では、季節の移り変わりと体調には深いつながりがあると考えます。
季節ごとの「養生法」を取り入れることで、体のバランスを整え、病気や介護状態に陥るのを防ぎます。
✅コツ:季節に合った生活習慣を
・春:肝をいたわる → 苦味のある山菜を取り入れる
・夏:心を冷やす → 暑さ対策+水分補給
・秋:肺を潤す → 大根や梨で潤いを補う
・冬:腎を守る → 体を温める黒い食材や根菜を活用
- 心のバランスも大切に
東洋医学では、心と体は切り離せないと考えます。
ストレスや孤独感は「気」の流れを滞らせ、体調不良や虚弱につながります。
✅コツ:人との交流、趣味、笑顔
・家族や友人との会話
・自然の中で深呼吸
・笑いの時間を大切にする
これも立派な「介護予防」の一つです。
東洋医学の視点から見ると、介護予防とは「毎日を丁寧に暮らすこと」。
自分の体と心の声に耳を傾け、未然に不調を防ぐことが大切です。
未来のために、今日からできる小さなケアをはじめてみませんか?